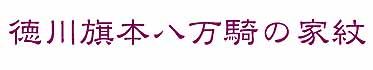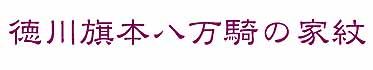| 
| 
| 
| 
|  |
| 家名
| 家紋
| 由緒
| 家名
| 家紋
| 由緒 |
| 飯河家
|

| 九曜
藤原魚名の末流とも平氏支流ともいう。飯河盛之の代に家康麾下に入った。
| 飯田家
|
作成中
| 丸に一本竹/丸に九枚笹
清和源氏伊那氏の一族。飯田宅重のとき徳川家との接触が始まった。 |
| 飯高家
|

| 並び九曜(角九曜)
伊勢の春日氏族とされる。戦国時代今川氏に属し、今川の倒れたのち家康に転じた。
| 飯塚家
|

| 九曜
畠山重忠の三男男衾重宗の後裔。飯塚綱重・忠重父子は大阪陣に従い功があった。
|
| 飯室家
|

| 丸に五本骨扇/花菱
甲斐源氏浅利氏の分かれ。甲州飯室に住んで飯室氏を称した。武田家滅亡後、家康に帰属し所領を安堵された。
| 池田家
|

| 丸に桔梗
源頼政の後裔で、親鸞とともに東国へ下り下妻にいついた宗重を祖とする。頼竜の代になって、母方の名字池田を名乗った。その子重利は大阪の陣に出ている。

|
| 池田家
|

| 揚げ羽蝶
池田輝政の子からは備前三十一万石、因幡三十二万石をあわせて大名家六家がある。輝政の四男輝澄と輝政の弟長吉の子孫から旗本家が出ている。

| 生駒家
|

| 波切車(生駒車)
生駒親正は讃岐高松十七万石の大名だったが、一正のとき御家騒動で除封。その孫高俊のときに一万石の大名として返り咲いた。

|
| 伊沢家
|

| 三つ寄せ笠
もと武田氏の一族で、武田信光が甲州伊沢に住んで地名を名字とした。武田家滅亡後、家康の招きでその麾下に加わった。
| 石尾家
|

| 丸に蔦
さきに出た荒木元清の三男治一のとき、石尾に改めた。花隈城落城後、秀吉に仕えた。大阪の陣では有馬豊氏の下で奮闘、のちに徳川秀忠属となった。
|
| 石谷家
|

| 九曜
藤原南家二階堂氏の分かれ。行清の代に西郷、清長の代に二階堂に復し、政清が遠州石谷に移り住んで以来、石谷氏を称したという。

| 石川家
|

| 笹竜胆
関ヶ原の後、美濃大垣城主となった石川家成の家から旗本家が三家出ている。

|
| 石河家
|

| 対い鶴
清和源氏頼親流で、はじめ柳瀬氏を称していた。摂津から陸奥に移ってから石河氏に改めた。石河光政は豊臣家から徳川家に転じ、関ヶ原で戦功を挙げた。

| 石野家
|

| 横木瓜
大和の旧族十市流中原氏の後裔。遠江石野に住んで石野と称した。今川氏に属し、石野広光以降は家康の麾下に入った。
|
| 石野家
|

| 三つ巴
播磨の赤松氏族。赤松氏真が石野の地頭職となり、石野を称した。
| 石原家
|

| 輪違いに一二の文字
清和源氏あるいは藤原氏族というが、甲斐三枝氏の後裔か。代々武田氏に仕え、家紋は信玄から与えられたという。政吉の代に武田滅亡。以後徳川氏に服属した。
|
| 石巻家
|

| 丸に三つ柏
藤原南家為憲流工藤氏の族。後北条氏に仕えていたが、石巻康敬のとき家康に転じた。
| 石丸家
|

| 丸に揚げ羽蝶
大友能道の後裔。一万田真能が、摂津の萱野郷石丸に住じて石丸を名乗った。石丸定政のとき家康の麾下に加わった。
|
| 伊勢家
|

| 対い蝶
伊勢平氏。鎌倉末期、俊継が天照大神の神託によって伊勢氏を称したという。室町時代は幕府権執事として権勢を振るった。代々足利家に仕えて、殿中での礼儀や儀式などを司った、有職・故実の家。

| 板倉家
|

| 三つ巴
備中松山五万石を筆頭に、上野安中、陸奥福島、備中庭瀬と四家の大名家を出した。旗本としては板倉重政の次男重直の流れがある。
|
| 板橋家
|

| 丸に三つ庵
桓武平氏秩父氏流豊島氏の分かれが、板橋に移って板橋氏を称した。小田原北条家滅亡後、板橋忠政は家康に服属した。
| 一尾家
|

| 竜胆車
もと久我氏。久我通堅の二男三休が九州に下り、豊後一尾庄に住んで一尾氏を称した。通春の代に家康から近江に千石の采地を受けた。
|
| 市岡家
|

| 二つ巴
木曽義仲の後裔といい、信州伊那の市岡に住んで市岡氏を称するようになった。忠次のとき家康に従って、武蔵に采地を与えられた。
| 市川家
|

| 丸に楓
甲州市川に住して、市川氏を称した。武田氏没落後、家康に転じ本領を安堵された。
|
| 市橋家
|

| 三つ盛菱
武藤長吉は幼時父を失い、母方の市橋長勝のもとで育ち、氏を市橋に改めた。

| 一色家
|

| 丸に二つ引
三河の吉良庄一色に住んで一色氏を称したのに始まる足利支族。室町時代は四職の一家として、羽振りがよかった。徳川時代の一色家は、さきの一色家に結ぶことは難しいようだ。

|