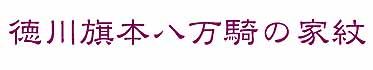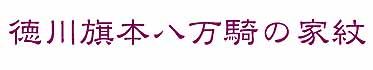| 
| 
| 
| 
|  |
| 家名
| 家紋
| 由緒
| 家名
| 家紋
| 由緒 |
| 仁賀保家
|

| 一文字三つ星
出羽の由利郡仁賀保に住み、仁賀保氏になったという、小笠原氏の一支族らしい。由利十二党の旗頭として古くから聞こえた。南北朝時代は北畠顕家に属し、数々の武功をあげた。関ヶ原の役で、仁賀保挙誠は、東軍に属し、上杉景勝と戦い、家康から感状を受けている。

| 仁木家
|

| 丸に二つ引両
清和源氏足利氏の一支族。三河の仁木に住んで仁木氏となった。

|
| 西尾家
|

| 櫛松
三河の幡豆郡から起こった吉良氏の一族で、同郡西尻に住んで西尾を称した。家康時代に戦功を積んだ西尾吉次の子忠永のあとは大名となった。この系とは別に吉次の養子利氏が関ヶ原の戦で家康使番として活躍、戦後千九百石となった。
| 西山家
|

| 九曜
もと武田家に仕え、武田家滅亡後に家康に転じた家。
|
| 蜷川家
|

| 合子に箸
蜷は巻貝の一種で「みな」ともいう。だから蜷川も皆川も家名としては同義。蜷川家は陸奥の新川郡蜷川から起こった。宮道氏の一族と称する。蜷川親満は徳川家康に仕え。親伯が綱吉治政下に八百余石の禄を与えられた。

| 丹羽家
|

| 直違い
関ヶ原の役にあたり、加賀小松十二万石の丹羽長重が隣封前田家ともめて、江戸に呼びつけられた、長重の弟長次も行動をともにして、品川に幽居の身となった。その後、長重は陸奥二本松の大名に返り割き、長次は千石の知行を与えられた。(児玉党裔)

|
| 丹羽家
|

| 雪輪にナズナ
多臣族良峰氏の裔と称し、尾張の丹羽郡の名を負うて丹羽を称した。正明のとき織田信長に仕え、その子正安も織田信忠・信雄に仕えたが、のち豊臣家に転じ、大坂役で討死をする覚悟だったが、戦火がおさまった後、家康に召し出されて仕えた。
|
|
|
|